テンコです♫
- 小さな子どもがいていつも部屋が散らかって困っている
- 「片づけなさい」といっても動いてくれない
- 片付けたそばからまた散らかされる
- 自分で片付けれるようになって欲しい
こんなお悩みありませんか?

もぉ~全っっっ然片付かない!
子どもに「片づけろ」って言っても全く片付けないしさ!

それ、「片付ける」の状態が理解出来てないかもしれないよ!
大人でも難しいお片付け。
幼児期の子どもにとっては、「片付いている」というのがどんな状態なのか、どうすればいいのか、など分からない事だらけ。
具体的な指示で、一緒に片付けながら教えて行く必要があります。
そんな「子どものお片付け」を子どもが上手に出来るように、保育園で働く整理収納アドバイザーの筆者が、保育園でのお片付けサポートをどんな風にしているかご紹介します。

実際どんな風に誘導してるか教えるね!
・子どもがワンアクションで片付けれる環境を作る
・子どものやる気を引き出す「よ〜い、どん!」などの声掛けをする
・次の事を始める前にお片付けをするよう声掛けを徹底して習慣化する
子どものやる気を引き出す声かけでオモチャの片付けを誘導する

・「よーいどん!」でお片付け競争をする
・子どもに「教えて」スタンスで子ども主導に誘導
・「どっちにする?」で自分で選んだ責任から行動を促す
・片付けも遊びの延長ですると盛り上がる
・一緒に片付けて具体的に指示
・「お片付けが上手だね!」の暗示
よーいどん!で片付け競争スタート
男の子によく効く「よーいどん!」。
最初は乗り気じゃなくても、誰か1人がやりだすと、闘争心に火がついてみんなで片付けてくれることも多いです。
このオモチャどこに片付けるか教えてくれる?
こっちは割と女の子が乗ってきてくれます。
「教えて」というワードが下からだからか、お姉さん気分をくすぐるのかな?
間に「なるほど!これは?」と合いの手を入れると片付け率アップです!(^^)!
コレとコレどっち片付けてくれる?
保育士の「てぃ先生」が保育番組の中で教えてくれたのですが、子ども自身が「自分で決める」という所が大事という事で、保育園で実践してみました。
そこで、「○○君、コレとコレどっち片付けてくれる?」と聞いてみました。
するとまんまと「○○君、こっち片付けるね!」と自ら動いてくれました。

てぃ先生、勉強になります!

今度やってみよ!
「OK!よ~し!じゃあ競争だ!」というとスピードアップします。
「バックしま~す!」で片付けも遊びの一環になるように楽しく

子どもにとって、生活を真似る事が遊びになります。なので、車のおもちゃを直す場所は駐車場。
「P」のマークがついた所なら喜んで直してくれますよ。
この時、「バックしま~す!ご注意ください。ピーッピーッピーッ」とか言って盛り上げてあげるとノリノリです(^^♪
一緒にオモチャを片付けて具体的に場所を指示
片付けは習慣です。
はじめの内は出来なくて当然なので、習慣になるまでは大人が一緒に片付けながら具体的な指示を出すのがいいと思います。
「片付けて」ではなく、「この箱に入れようね」「ここにコレを並べてくれる?」「コレをこの中に入れてくれる?」など具体的な行動を小さな子には指示してみて下さい。

子どもに伝わる言葉で具体的に

「片付けて」じゃ伝わらないんだね
「片付け」自体何かが分かってないかもしれませんからね。
モチロン、相手のある事なので100%動いてくれるワケではありませんが、不機嫌でなければ1歳くらいの子どもでも片付け出来ます。
○○ちゃん(君)はお片付けが上手だねと刷り込む
お片付けが少しでも出来たら、「お片付け出来たね、○○ちゃん(君)はお片付けが上手だね」と声をかける様にしています。
もちろん本心で言うのですが、これは刷り込みでもあります(笑)
「お片付けが出来る私(ボク)」という事を自分で思うようになれば、本当にそうなると思うからです。
子どもがワンアクションでオモチャを片付けれる環境を作る

・ワンアクションで完了!ハードルの低い収納
・イラストや写真で指示
・身体機能に見合った収納へ
ワンアクションで完了!ハードルの低いオモチャ収納
子どものお片付けはとにかくハードル低く。
基本的にワンアクションで完了する収納がオススメです。
- 入れる
- 置く
- 掛ける
- 貼る

マグネットなどで「貼る」もワンアクションだよ

片付けのハードルをとことん下げろって事ね。
年齢が上がるともう少し複雑な収納も可能ですが、小さい子に合わせた収納にしておくと、皆のハードルも下がるので、楽です。
取り出す際は2アクションでも可能なようですが、戻すのは難しいようです。出すより戻す方が難しいのは大人でも同じかな、と思います。
1ジャンル1ボックスにオモチャ収納
ぬいぐるみ、本、お医者さんセット、積み木、などジャンルごとに分類するのは1歳児〜2歳児でも出来るようです。
あとは大きなボックスなどに、先程のワンアクションで収納出来るよう配置します。
イラストや写真でオモチャをしまう位置を指示
字の読めない子どもとの共通言語はイラストや写真です。
おもちゃのイラストや写真を、収納する場所に貼って「ここに戻すよ」と誘導します。
戻す場所が分かりやすいおもちゃは、保育者が声をかけなくても戻せていることもしばしば。
大人でも、戻す場所が分かっていると片付けのハードルが下がり、素早く片られます。

子どもに優しい収納は皆にも優しい
一つのおもちゃでいくつもパーツがあるような、パズルの様なものはカラーシールで色分けすると無くしません。
パズルごとにピースの裏と台紙に同じシールを貼っておけば、スイスイ分ける事が出来ますよ。
お片付けを遊びにする工夫
お片付けを嫌がるのは、面倒くさいし、難しいと思っているから。
ならば、お片付けを楽しく仕向ける方法があります。
投げても危なくないお手玉やボールは、「玉入れ大会」に。
皆、喜んでかごに投げてくれますよ!大人が上手くキャッチ出来れば片付きます(笑)

時間はかかりそうだけど、盛り上がるかも

やってる内に自分も楽しくなるよ!
心に余裕があれば、やってみて下さい。
身体機能に見合った余白のある収納法へ
機能が未発達な幼児にとっては出し入れの余白がないとハードルがあがります。
身体機能に見合った配置や余白が必要です。
大人にとってはシンデレラフィットなんてのが理想形ですが、子どもでは引っかかって出し入れがしにくかったりします。
すると元に戻せなくて放置、になります。
まだ入りそうでも、7割収納までに抑えます。

上下左右に余白が作ってね

シンデレラフィットは大人向きなんだね
また、高さも重要。
自分で片付けさせる前提なら、子どもの胸の高さくらいまでの収納がベストです。
なので、年齢差がある場合は上の子が上、下の子が下ですね。
子どもの安全性を考慮したオモチャ収納
ここで注意したいのが、上には落ちてきても安全なものを置くようにします。
軽いものや、ぬいぐるみなどの布類がいいですね。
小さいお子さんに触らせたくないものを、大人の都合で高い場所に置く事もあると思いますが、子どもは好奇心から、椅子などで足場を作って登ってでも取ろうとする事があります。

触って欲しくないものほど触ろうとするよね
収納家具は、子どもが押したくらいでは倒れないようなしっかりとしたものを選ぶようにします。
次の行動の前に今使っているおもちゃを直す習慣づけが大事

・次の行動に移る前に、今使っている遊び道具を片付けるよう声をかけて一緒に片付ける
・片付けの先に「お楽しみ」を用意する
次の遊びをする前に自分が出したオモチャを片付けるように声をかける
早く片付いて欲しくて親が全部片づけてしまう気持ちは分かります。でも、それではいつまでも子どもは親がしてくれると勘違いしてしまいます。
1つでもいいので、自分で遊んだモノは子ども自身で片付けたという事実を積み重ねていくことが大事だと思います。
実際、園でも絶対に片付けようとしない子もいます。でも、それを許してしまうと、これから先も「自分が片付けなくても誰かがやってくれる」と学んでしまいます。

3,4歳頃になると、ずる賢い子がいます
そういう子は手を変え品を変え、「片づけた」という事実を作るように粘り強く声掛けしています。
子どもだけに任せておいたらラチがあかないので、大人が「手伝う」というスタンスで一緒に片付けてあげて下さい。
オモチャを片付けしたら○○しようねで意識をこっちに向ける
お片付けが終わらないと次に進めない。この声掛けで、率先して片付けてくれる子もいます。
特におやつの前は(笑)
まずはおやつの前だけでも、片付けの習慣をつけてみるといいですね。ここは根気よく習慣づけをしていく必要があります。
「おやつ」に反応しない時は、実物を見せます。おやつがイメージ出来てない事があるので。
まとめ|子どもは成長の途中段階。出来なくても気長に受け止めよう

子どもにおもちゃを片付けさせる方法は次の通りです。
・子どもワンアクションでおもちゃを片付けれる環境を作る
・子どものやる気を引き出す「よ〜い、どん!」などの声掛けをする
・次の事を始める前にお片付けをするよう声掛けを徹底して習慣化する
性格や環境によっても違ってはくるのですが、どれかヒットする方法が見つかればいいなと思います。
ではでは。
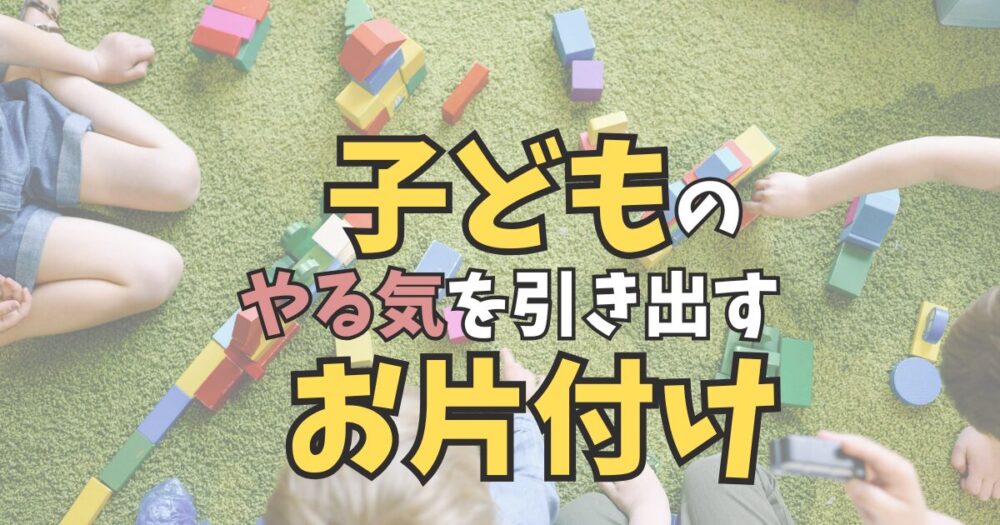

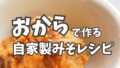
コメント